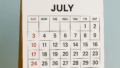駅から少し離れた路地に、小さな赤ちょうちんが灯っている。
「居酒屋 なごみ」。
木の引き戸の向こうから、笑い声と焼き魚の香りが漏れてくる。
寒い夜には、その光と匂いがまるで暖炉の火のように感じられる。
この店は、会社帰りによく立ち寄る場所だ。
きっかけは、3年前の冬。
同僚に誘われて初めて訪れたとき、狭い店内に漂う温かさと、どこか懐かしい雰囲気に心を掴まれた。
引き戸を開けると、カウンター越しに女将さんの笑顔が見える。
「おかえりなさい」
常連客には、そんなふうに声をかけてくれる。
初めて来たときには「いらっしゃいませ」だったけれど、通い始めて半年も経つと、自然にその言葉が「おかえり」に変わった。
カウンター席には、顔なじみの常連さんが数人。
一番奥の席に座っているのは、口数の少ない中年の男性。
いつも静かに日本酒を飲み、帰り際に必ず「ごちそうさま」と深く頭を下げる。
その姿は、無駄がなく、背筋がぴんと伸びていて、なぜか見ているだけで気持ちが引き締まる。
テーブル席では、若い会社員たちが賑やかに盛り上がっている。
笑い声とジョッキがぶつかる音。
その間を縫うように、女将さんとアルバイトの青年が料理を運んでいく。
まずは、生ビールを注文する。
グラスに注がれる黄金色の液体、きめ細かい泡。
最初のひと口は、いつだって特別だ。
冷たさが喉を滑り落ち、体中に「今日もお疲れさま」という信号が広がる。
お通しは、ほうれん草のおひたしと、かぼちゃの煮物。
こういう素朴な味が、なぜか一番落ち着く。
壁に貼られた手書きの短冊メニューを眺める。
「秋刀魚の塩焼き」「出汁巻き卵」「鶏の唐揚げ」「おでん各種」…。
季節ごとに変わるおすすめメニューは、女将さんの仕入れによって決まるらしい。
今日は寒いので、おでんを頼むことにした。
ほどなくして、湯気の立つ土鍋が目の前に置かれる。
大根、卵、ちくわ、厚揚げ――出汁の香りがふわりと漂う。
箸を入れると、大根が簡単に崩れ、じゅわっと出汁がしみ出してくる。
口に入れた瞬間、熱さと旨みが広がって、自然と目を閉じてしまう。
「今日は寒いから、出汁も少し濃いめにしてるのよ」
そう言って笑う女将さん。
その一言だけで、ただの食事が特別になる。
カウンターの隣に座っていた常連さんが、ぽつりと話しかけてきた。
「ここのおでんは、冬の名物だよ。気づけば毎年これを食べに来てる」
その言葉に、私は少しうなずきながら、またひと口、大根をかじった。
居酒屋には、不思議な力があると思う。
ここでは、肩書きや立場が溶けてしまう。
会社員も、職人も、学生も、みんなただの「飲みに来た人」になる。
初めて会った人同士が自然に会話を始め、気づけば笑い合っている。
そんな空間を作っているのは、きっと料理でもお酒でもなく、人だ。
女将さんの「おかえりなさい」という言葉。
常連客の「お先に失礼します」という一声。
その小さなやりとりが、この店を温めている。
時計を見ると、もう終電の時間が近い。
最後に熱燗を一合だけ頼む。
白い徳利と、お猪口が目の前に置かれる。
お猪口を手に取り、ゆっくりと口に運ぶと、やわらかな熱が体を包み込む。
「また来てくださいね」
女将さんの声に送られて、のれんをくぐる。
外の空気は冷たく、吐く息が白い。
でも、胸の中にはじんわりとした温かさが残っている。

家に帰ってからも、その温かさは消えなかった。
居酒屋というのは、料理やお酒だけでなく、「時間」と「空気」を味わう場所なのだと思う。
誰かと語らい、笑い、時には黙って杯を傾ける。
そんなひとときが、日々の疲れをそっと癒してくれる。
また明日も仕事がある。
でも、その帰り道に、あの赤ちょうちんの灯りがあると思うと、不思議と心が軽くなる。
居酒屋とは、日常の中にある小さな港だ。
どこから来た人でも、一時だけ船を停め、体と心を休められる場所。
そして、再び自分の海へと漕ぎ出していくための、静かな寄港地なのだ。
今夜もまた、路地の先で、赤いちょうちんが灯っている。
きっと、あの店には誰かの笑い声が響いているだろう。
私はその光景を思い浮かべながら、少しだけ胸が温かくなるのを感じていた。
週末の夜、久しぶりに「なごみ」の暖簾をくぐった。
外は冷たい雨が降っていたけれど、戸を開けた瞬間に、あのやわらかな熱気と匂いが体を包み込む。
女将さんが顔を上げて、「おかえりなさい」と微笑む。
その一言だけで、外の寒さも雨も忘れた。
カウンターの端には、見覚えのある常連さんが座っている。
軽く会釈を交わし、私は空いている席に腰を下ろした。
運ばれてきた熱燗を一口含むと、胸の奥まで温かくなる。
こんな瞬間があるから、私はまたここに来てしまうのだろう。
料理を食べ、少し話し、少し黙る。
時計の針は静かに進んでいくけれど、この店の中では、時間は穏やかに流れている。
ここでは、終電や翌日の予定なんて、ほんの少し遠くの出来事のように思える。
帰り際、女将さんが小声で言った。
「また、疲れたらおいで」
その言葉を背中に受けて暖簾をくぐる。
路地に出ると、雨はもう上がっていて、石畳が街灯の光を映していた。
胸の中には、熱燗の温もりと、人の声の温もりが残っている。
居酒屋は、ただお酒を飲む場所じゃない。
そこは、日々を生きる私たちの、小さな避難所だ。
またきっと、あの赤ちょうちんを目指して歩くだろう。
そのときも、あの灯りは変わらず、私を迎えてくれるに違いない。