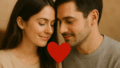「ラスト1球――気ぃ抜くなよ!」
キャッチャーミットにボールが収まる音と同時に、
ベンチから誰かが声を張った。
202X年、夏。
甲子園の県予選、準決勝。
9回裏、2アウト、フルカウント。
俺は、マウンドの上に立っていた。
小さい頃から野球をやってきた。
親父が元高校球児で、俺も自然とグローブを握るようになった。
地元の少年野球チームに入り、中学では軟式、そして高校では硬式へ。
3年間、投げて、投げて、投げ抜いた。
1年の夏はベンチ外。
2年の夏はベンチ入りしたが、登板はゼロ。
そして、3年。俺はエースナンバーを背負った。
たぶん、俺の人生で一番野球に真っすぐだった季節だった。
早朝のランニング、真冬のノック、誰もいないグラウンドでの投げ込み。
苦しいと思ったことは何度もある。
でも、逃げたいと思ったことは、一度もなかった。
仲間と笑い合い、泣き合い、バカみたいに夢を語り合った。
「甲子園、行こうな」
その言葉を、信じていた。
そして迎えた、最後の夏。
準決勝の相手は、去年の優勝校だった。
強豪だ。プロ注目のスラッガーもいる。
試合は、最初から気が抜けなかった。
3回に2点を先制されたが、5回裏に同点に追いついた。
6回からは、一進一退の攻防が続いた。
そして迎えた9回裏。
同点、ランナーなし、2アウト。
打席には、相手の4番。
その打者は、この日すでにヒットを2本打っていた。
マウンドからキャッチャーを見る。
サインは――ストレート、外角。
俺は首を横に振った。
次のサイン――スライダー。
もう一度首を振った。
最後のサイン――インハイ、ストレート。
俺は頷いた。
あの日、ひとりで100球以上投げた練習の先に、この1球があると思った。

背中のゼッケン「1」が、やけに重たく感じた。
スタンドには、チームメイトの保護者、吹奏楽部、OB、生徒会。
そして、俺の家族もいた。
深呼吸をする。
風の音が耳の奥でひゅう、と鳴った。
踏み出す、最後の1球――
俺の人生で、いちばんまっすぐなボールを投げた。
結果は――ホームランだった。
バットに当たった瞬間、音で分かった。
打球は高く、長く、空に伸びていった。
レフトの背中が、ゆっくりとフェンスに向かうのが見えた。
球場が静まりかえった。
ほんの一瞬、時間が止まったようだった。
それから、歓声が波のように押し寄せた。
相手ベンチが沸き、ホームインする4番にチームが駆け寄る。
その光景を、俺はマウンドの上から見つめていた。
負けた。
そう思った瞬間、涙があふれた。
しゃがみ込みたかった。
でも、ふらつきながらも立っていなければいけないのが、投手だった。
キャッチャーが、静かにミットを外して近づいてきた。
「お疲れ」
その一言だけで、もうダメだった。
俺は、泣きながらマウンドを降りた。
ベンチに戻ると、監督が目を真っ赤にして立っていた。
「ナイスピッチングや」
その言葉を聞いたとき、悔しさよりも、不思議と“やりきった”という気持ちの方が勝っていた。
ロッカールームに戻ると、誰もしゃべらなかった。
ただ、みんなが泣いていた。
泣くことでしか、この終わりに向き合えなかった。
その夜、布団に入っても眠れなかった。
試合の最後のシーンが何度もリピートされた。
でも、何度見ても、あれが俺にできる最善の1球だったと思う。
だから、後悔はしていない。
本当に、していない。
それから数年が経った。

大学に進学し、今は地元の企業で働いている。
野球は、もうしていない。
でも、野球が教えてくれたことは、今もちゃんと心の中にある。
粘ること、信じること、最後まで投げ抜くこと。
仕事でうまくいかないとき、ふと思い出す。
あの夏、あの1球。
打たれて、負けて、泣いたけれど、
それでも“最後まで自分を信じて投げた”という記憶は、いつも心を支えてくれる。
人生には、いくつもの“最後の1球”がある。
就職の面接、誰かへの告白、大切な決断。
そのたびに、俺は思い出すのだ。
あの、空に伸びていった白球を。
そして、もう一度マウンドに立つような気持ちで、
一歩、前へ進む。
あの夏から、5年が過ぎた。
今年の夏も、蝉の声が町に響いている。
甲子園予選の季節になると、決まってあの日のことを思い出す。
あれが、俺の“野球人生の最後の一球”だった。
でも、人生の「最後」ではなかった。
今は、地元の中学で部活動のコーチをしている。
会社帰りに、時間が合えばグラウンドに立つ。
汗だくになりながらボールを追う子どもたちの姿を見ると、自分の中の何かが呼び起こされるような気がする。
「フォーム、もう少し下半身を使ってみて」
そう声をかけると、ある生徒が振り返って言った。
「コーチ、甲子園行ったことあるんですか?」
俺は少し笑って、こう答えた。
「行けなかったよ。でもな、最後の1球は、悔いなく投げた」
それだけで、その子は「すごいなあ」と目を輝かせた。
それで、よかったのかもしれない。
勝てなかったけれど、逃げなかった。
負けたけれど、投げ切った。
あの一球を、胸に持ったまま、これからも歩いていける。
もう一度、あの日のマウンドに立てたとしても、きっと俺は、
同じ球を、同じ場所へ、もう一度投げるだろう。
そして、
空へ吸い込まれていく白球を、
もう一度、笑って見送れる気がする。
これが、俺の“最後の一球”の、その続きの物語。
終わりじゃなくて、始まりだったんだ。