朝食を食べる時間は、一日の中でもっとも静かな瞬間かもしれない。
まだ街全体が完全には目を覚ましていない、やわらかな光の中で、湯気の立つマグカップや焼きたてのパンの香りが、私を現実へと連れ戻してくれる。
今日は少し早起きをした。
窓を開けると、朝の空気が頬を撫でる。
夜の冷たさがわずかに残っていて、深く息を吸うと、胸の奥まで澄みわたるようだ。
鳥のさえずり、遠くから聞こえる新聞配達のバイクの音。
そのすべてが、朝の合図だった。
私の朝食は、決して豪華ではない。
トースト一枚にバターを塗り、半熟の目玉焼きをのせる。
サラダはレタスとトマトときゅうり、そして少しのオリーブオイル。
飲み物は、ブラックコーヒー。
でも、このシンプルなメニューが、なぜか一番落ち着く。
食パンが焼ける香りが部屋に広がり、バターがじわっと溶ける瞬間に、なんとも言えない幸福感がある。
食卓に座り、まずはコーヒーをひと口。
熱さと苦みが舌に広がって、頭の奥がじわじわと動き始める。
「さあ、今日も始まる」という気持ちになる。
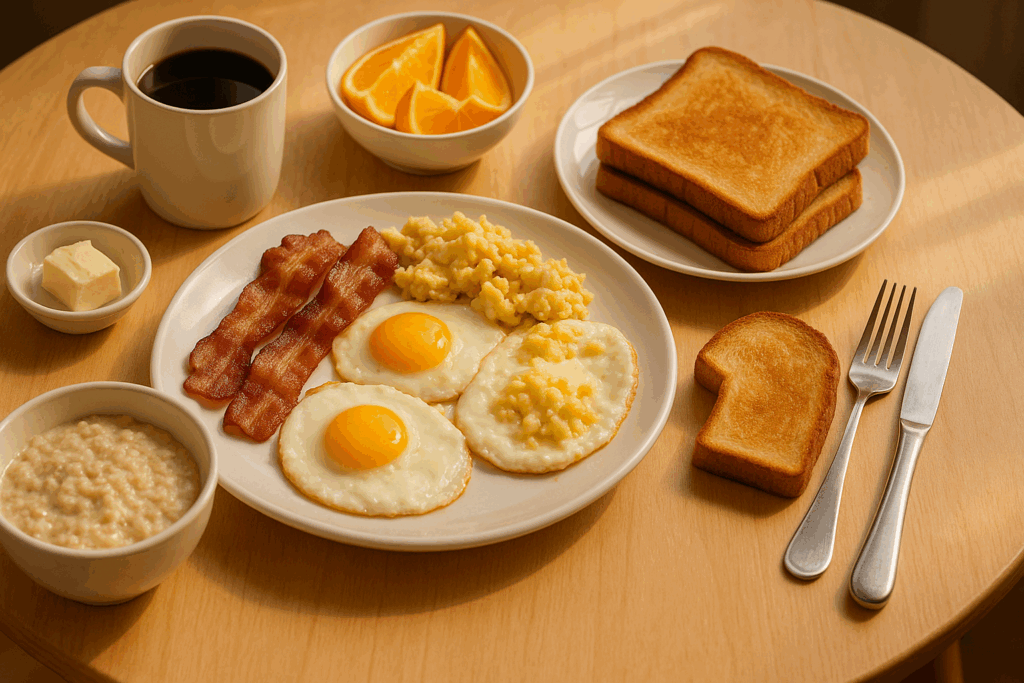
子どものころ、母の作る朝食はいつも決まっていた。
ご飯と味噌汁、焼き魚、卵焼き、そして小さな漬物。
学校に行く前のあの時間は、眠くてぼんやりしていたけれど、味噌汁の湯気の向こうに見える母の横顔を、なぜか今でもはっきり覚えている。
「朝ごはん食べないと元気出ないよ」
母はそう言って、急かすように味噌汁を差し出した。
当時はその意味を深く考えなかったけれど、大人になった今ではわかる。
あれはただの食事ではなく、母からの“お守り”だったのだ。
社会人になってから、朝食はおろそかになりがちだった。
朝の時間は慌ただしく、トーストをかじりながらメールをチェックし、コーヒーを片手に家を飛び出す。
時にはコンビニのおにぎりを駅のホームで食べることもあった。
でも、そんな日々の中で、ふと気づいた。
朝食をきちんと食べた日と、そうでない日では、一日の気分が違う。
しっかり朝食を取った日は、午前中の集中力が続くし、心にも余裕が生まれる。
逆に、何も食べずに出かけた日は、どこか落ち着かず、空腹よりも“欠けた感覚”が残る。
それからは、どんなに忙しい日でも、5分だけでも朝食の時間を取るようになった。
たとえインスタントスープとトーストだけでも、自分のために用意した食事は、心を整えてくれる。
休日の朝は、少し特別だ。
平日よりも遅く起き、ゆっくりとキッチンに立つ。
ベーコンとソーセージを焼き、ふわふわのスクランブルエッグを作る。
パンは厚切りで、バターをたっぷり。
大きめのマグカップにカフェオレを注ぎ、フルーツを添える。
窓から差し込む光の中で食べるその朝食は、旅先のホテルのモーニングのようだ。
誰に見せるわけでもないけれど、自分だけの贅沢。
食後には読書をしたり、音楽を聴いたりしながら、ゆったりと時間を味わう。
旅先で食べる朝食も、また格別だ。
ビュッフェの並んだ料理を前に、ついあれもこれもと皿に盛ってしまう。
ホテルの食堂に流れる軽やかな音楽、窓の外の景色、知らない土地の空気。
そのすべてが、日常の朝食とは違う輝きを持っている。
旅先の朝食を食べながら、「この時間がずっと続けばいいのに」と思うことがある。
でも、旅が終わるからこそ、その朝食は特別な思い出になるのだろう。
最近、朝食を通して気づいたことがある。
それは、朝食は単なる食事ではなく、“心の準備運動”だということ。
朝食を食べることで、体だけでなく心も一日を迎える姿勢になる。
たとえ前日に嫌なことがあっても、朝食の時間が、気持ちを切り替える小さな儀式になってくれる。
だからこそ、私はこれからも、朝食を大切にしたい。
豪華でなくてもいい。
パンでもご飯でも、スープだけでも。
その時間を持つことが、一日の質を変えてくれるのだから。
今朝もまた、トーストをかじりながらコーヒーをすする。
カレンダーを見ると、今日は少し忙しくなりそうだ。
でも、こうして朝食を食べたことで、私はきっと大丈夫だと思える。
朝食は、体を動かすエネルギーであると同時に、心にとっての灯りのようなものだ。
それがあるだけで、一日の始まりが少し明るくなる。
そして、明日もまた、同じように朝食をとるだろう。
それは習慣であり、ささやかな幸せであり、私にとって欠かせない時間なのだ。
食器を片付け、コーヒーカップをすすぎながら、ふと窓の外に目をやると、
朝日がビルの間からまっすぐに差し込んでいた。
光はテーブルの端に置いた小さな花瓶を照らし、その中の一輪のガーベラが淡く輝いている。
その光景を見た瞬間、なぜか胸の奥が温かくなった。
何でもない朝なのに、「ああ、今日もいい日になりそうだ」と素直に思えたのだ。
朝食は、ただお腹を満たすための時間じゃない。
こうして、静かに自分と向き合い、小さな幸せを見つけるための時間でもある。
パンの香り、湯気の立つスープ、カップから漂うコーヒーの匂い。
その全部が、今日を優しく始めるための合図だ。
この先、忙しい日も、疲れた日も、きっと何度も訪れるだろう。
それでも、朝食のひとときだけは、変わらず私を支えてくれる。
たとえ形やメニューが変わっても、その温もりは同じまま。
明日の朝も、またこのテーブルで。
湯気の向こうに、新しい一日を迎える自分がいる。
それだけで、十分幸せだと、私は思う。


